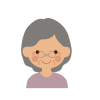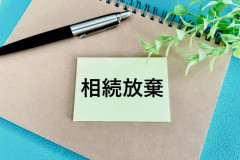相続
|
相続とは |
相続とは・・・
個人が亡くなったときに、その人のすべての権利・義務を家族等が引き継ぐことです。亡くなった人を被相続人財産を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続人は民法で定められた相続順位に基づいて決められます。被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言書に基づいて相続手続が行われ、無い場合には法定相続人によって協議を行い全員の合意のうえで行います。
相続手続には専門的な知識が必要となる場合もあるため、専門家にご相談することをお勧めします。
|
法定相続人と法定相続分 |
相続開始時に相続人となる人(法定相続人)や相続順位と承継する財産の割合(法定相続分)については民法で定められています。
◆配偶者➡常に相続人
◆相続順位➡第1順位~第3順位
①第1順位▶直系卑属(子ども・孫など):子どもが死亡している場合は孫が相続人になります。(代襲相続)
②第2順位▶直系尊属(両親・祖父母など):第1順位の相続人が存在しない場合に相続人になります。両親が死亡している場合は祖父母が相続人になります。
③第3順位▶兄弟姉妹:第1順位・第2順位の相続人が存在しない場合に相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が相続人になります。
相続人と法定相続分の割合
①法定相続人が配偶者と第1順位(子ども・孫など)
|
配偶者 |
第1順位 |
||
|
1/2 |
1/2 |
||
②法定相続人が配偶者と第2順位(両親・祖父母など)
|
配偶者 |
第2順位 |
||
|
|
2/3 |
1/3 |
|
③法定相続人が配偶者と第3順位(兄弟姉妹)
|
配偶者 |
第3順位 |
||
|
|
3/4 |
1/4 |
|
※法定相続人が「配偶者のみ」「第1順位のみ」「第2順位のみ」「第3順位のみ」の場合にはそれぞれが全ての財産を相続します。
※第1順位~第3順位の法定相続人が複数の場合はその人数で均等に分けます。
※第3順位(被相続人の兄弟姉妹)が相続人の場合、半血兄弟の法定相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2と定められています。
|
相続手続 |
遺言書の確認
遺言書の有無や種類によって相続手続に違いがあります。遺言書が存在しない場合には相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
◆遺言書がある場合
原則として遺言書の内容に従って相続手続(遺言執行)を行います。ただし、法定相続人全員の合意により遺言書とは異なる内容の遺産分割も可能です。
①自筆証書遺言
被相続人の遺品の中や自宅(書棚・仏壇など)で見つかることや、貸金庫・友人知人・士業などに預けている場合もあります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の申立てを行い検認の終了後に検認済証明書の交付を申請します。自筆証書遺言での相続手続には家庭裁判所で検認を受けた遺言書であることを証明する必要があります。
また、遺言者が令和2年7月10日より開始された「自筆証書遺言保管制度」を利用していた場合は検認の必要はありません。法務局に遺言書保管事実証明書の交付請求を行うことにより法務局で遺言書が保管されているか否かを確認することができます。しかし遺言書の内容までは確認することは出来ないので、別途遺言書情報証明書の交付申請を行い遺言書の内容を確認することが出来ます。但し、遺言書の原本は返還されないので相続手続は遺言書情報証明書を使って進めていきます。
②公正証書遺言
公正証書遺言の検索システムを利用して全国の公証役場で「遺言公正証書」の有無やどこの公証役場で保管されているか確認することができます。公正証書遺言の場合は自筆証書遺言と異なり家庭裁判所での検認は不要です。
◆遺言書が無い場合
法定相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申立てます。
相続人の調査
相続が開始されたら、全ての相続人(法定相続人)を調査し確定する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を取得して相続人の範囲を確定します。知らない相続人の存在が判明することもあります。
遺産分割協議は、全ての相続人で行う必要があるので一人でも欠けていたら無効になります。また、相続手続で戸籍謄本の提出が必要になります。
相続人の調査が完了したら、それらの資料をもとに相続関係説明図を作成すると手続きがスムーズに進みます。
財産の調査
被相続人のプラス・マイナス全ての財産を調査して確定します。相続の承認や放棄の判断以外にも、遺産分割協議や相続税の申告にも必要となります。遺言書やエンディングノートなどが見つかればスムーズに進みますが、無い場合には相続人が調査しなければなりません。また、遺言書やエンディングノートに記載されていない財産が存在する可能性もあります。
◆プラスの財産
①不動産
権利証(登記済証)・登記識別情報や固定資産税課税通知書などで被相続人が所有していた不動産を調べます。また、不動産があると思われる市区町村で「名寄帳」を取得して所有する全ての不動産を確認することが出来ます。
②預貯金
通帳やキャッシュカード・郵便物などから金融機関の口座を特定します。(「全店照会」で他の支店の口座の有無を照会することも出来ます。)口座の特定が出来たら金融機関に「残高証明書」を請求します。
③有価証券
証券会社がわかっている場合は、口座の「残高証明書」を直接請求します。不明な場合は、証券保管振替機構に「登録済加入者情報の開示請求」を行い確認します。
④債権
被相続人が誰かに金銭を貸していたり、被害を受けた際の損害賠償などが該当します。契約書や郵便物などの書類を探して調査します。また、被相続人が個人事業主だった場合には、取引先への売掛金の残高も債権になります。
◆マイナスの財産
金融機関からの借入や住宅ローンなどが代表的なものですが、未払いの税金や公共料金などもマイナスの財産(負債)になります。また、相続開始時の被相続人の負債は相続財産の価額から差し引くことが出来ます。
自宅で郵便物や書類などを調べたり、預金通帳やクレジットカードの確認、親族や友人・知人に尋ねることで判明することもあります。登記簿謄本を取得すれば抵当権の設定で借入金の有無が確認できます。また「信用情報機関」に情報開示請求をすることにより確認することが出来ます。
相続の承認と放棄
「相続の承認」と「相続の放棄」は熟慮期間内に決定する必要があります。
相続は被相続人が死亡したときから開始しますが、相続人は原則として自分に相続が開始したことを知ったときから3か月の熟慮期間内に相続を承認するか、放棄するかの選択をしなければなりません。
◆相続の承認
①単純承認
相続人が被相続人の一切の権利義務(プラス・マイナス全ての財産)を無限に承継します。熟慮期間内に承認・放棄の選択をしなかった場合や、相続財産の処分や名義変更などを行った場合には単純承認をしたことになります。(法定単純承認)被相続人の借金などを背負うこともあるのでキチンと調査をしたうえで決定するのが望ましいです。
②限定承認
相続財産の範囲内でマイナスの財産(負債など)を清算して残額があればプラスの財産を承継できます。熟慮期間内に共同相続人全員で家庭裁判所に申述をします。
◆相続の放棄
相続放棄をした場合は初めから相続人でなかったとみなされます。相続放棄を選択する場合は、熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。また、相続放棄をした場合には代襲相続は起きません。
遺言執行と遺産分割協議
遺言執行とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行うことです。遺言書で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が遺言執行を行い、遺言執行者がいない場合は相続人が行います。遺言執行者には遺言書の内容に従い忠実に実行する義務があります。
遺産分割協議とは、遺言書が無い場合や遺言書の内容とは異なる内容で遺産を分割したい場合に、相続人全員で協議をします。全員の合意で協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
不動産・有価証券・自動車などの財産の名義を相続人に変更します。不動産に関しては令和6年4月より相続登記が義務化されました。これは、相続登記が任意だったために「所有者不明土地」が全国で増加し社会問題となっています。この問題を解決するため法律が改正されて義務化されることになりました。
正当な理由なく相続登記がされなかった場合には10万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続税と贈与税
◆相続税
相続税とは、亡くなった人(被相続人)から相続または遺贈により財産を取得した場合、財産を取得した人(相続人・受遺者)に課される税金です。
◆贈与税
贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた場合に財産を取得した人に課される税金です。相続税の課税逃れを防ぐ役割があるので相続税の補完税と言われています。