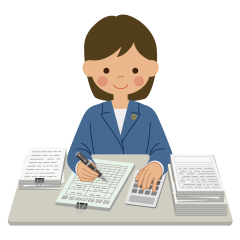相続税と贈与税
|
相続税と贈与税 |
|
相続税 |
相続税は、死亡した被相続人から財産を取得した場合に課される税金ですが、相続財産の全てが課税対象になるわけではありません。
◆相続税の課税対象になる財産
①本来の相続財産
相続や遺贈により取得した財産的価値のある全ての財産が対象です。
〇土地・建物・現金・預貯金・有価証券・貴金属・宝石・事業用財産など
②みなし相続財産
民法では相続財産に該当しなくても、相続税法では相続財産として相続税の対象にされる財産です。
〇死亡保険金・死亡退職金など
500万円×法定相続人の数がそれぞれの非課税限度額になります。
③生前贈与財産
被相続人が生前に贈与した財産のうち相続財産に含められる財産です。
〇相続開始前3年以内に受け取った贈与財産(➡2024年1月1日以降の贈与から7年以内に延長されました)
〇相続時精算課税制度による贈与財産
◆相続税の非課税財産
相続税の課税対象にならない財産です。
〇墓地・墓石・仏壇・仏具など 宗教的な財産
〇死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
〇弔慰金
◆債務控除
相続財産のうち、プラスの財産からマイナスの財産の価額を差し引いて相続税を課税します。
〇被相続人の債務
借入金・未払いの 医療費や税金など
〇葬式費用
通夜・葬儀の費用
◆基礎控除
相続税の基礎控除=3,000万円✛600万円×法定相続人数
※相続税法では相続放棄をしても法定相続人に含まれます。
相続税の計算と納付
課税価格の計算
相続や遺贈などにより取得した財産から非課税財産や債務・葬式費用を差し引いて各人の課税価格を計算します。
本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産-債務控除=各人の課税価格
課税遺産総額の計算
各人の課税価格の合計額から基礎控除を差し引きます。
相続税の総額の計算
課税遺産総額を相続人ごとに法定相続分で仮に按分して(※)税率を掛けそれぞれの税額を計算し、それらを合算して相続税の総額を算出します。
法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額
相続税の税率
|
相続税速算表(平成27年1月1日以降) |
||
|
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
― |
|
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円 超 |
55% |
7,200万円 |
各相続人の税額を計算
相続税の総額を各相続人が実際に相続した課税価格に応じた割合で按分して、各人の相続税額を算出します。
相続税額の加算と控除
⑴相続税額の2割加算
被相続人の配偶者や一親等の血族(両親・子供)でない場合には算出税額の2割が加算されます
⑵税額控除
①配偶者の税額軽減
配偶者の取得した財産が次のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です
◆1億6,000万円
◆法定相続分
②贈与税額控除
相続開始前3年以内に贈与を受けて贈与税を課税された人はその贈与税を相続税から控除することができます
③未成年者の税額控除
④障害者の税額控除
相続税の申告と納付
⑴相続税の申告
申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日です。相続財産が基礎控除以下の場合には申告は不要ですが、配偶者の税額軽減の特例などを受ける場合には納税額が0円であっても申告をする必要があります。提出先は被相続人が死亡時の住所地の管轄税務署長です。
申告書の作成は、相続や遺贈などにより財産を取得した人が共同または個別に作成して提出できます。また、e-Tax(電子申告)での提出も可能です。
⑵相続税の納付
原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日までに金銭で一括納付します。金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には「延納」や「物納」が認められています。(➡相続税の申告期限までに手続が必要です)
|
贈与税 |
贈与税は、生存している個人(贈与者)から財産を取得した人(受贈者)に対して課される税金です。相続税に比べて税率が高く負担が重くなっています。
◆贈与税の課税方式
贈与税の課税方式には暦年課税制度と相続時精算課税制度があり、贈与者ごとに選択することが可能ですが、相続時精算課税を選択した場合には暦年課税には戻れません。
①暦年課税制度
毎年1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。財産の価額の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合に申告及び納税をする必要があります。
②相続時精算課税制度
贈与者が原則60歳以上の父母や祖父母であり、受贈者が18歳以上の子や孫である場合、累計で2,500万円が非課税になり、これを超えた金額に一律20%が課税されます。この制度では贈与時に贈与税は軽減され、生前に贈与された財産は相続時に相続財産に加えられ相続税で精算されます。
◆贈与税の課税対象になる財産
①本来の贈与財産
贈与により取得した経済的価値のある財産が対象となります。
〇現金・預貯金・有価証券・不動産など
②みなし贈与財産
本来は贈与財産ではありませんが、贈与財産と同様に扱われる財産です。
〇生命保険金▶保険料の支払人でない人が生命保険金の受取人だった場合など
〇低額譲受▶市場価格よりも著しく低い価格で資産を譲り受けた場合の差額を贈与とみなされ、贈与税が課税されることがあります
〇債務免除▶借金をしていた人が、その借金の返済を免除してもらった場合の金額
◆贈与税の非課税財産
〇法人から贈与により取得した財産▶個人からの贈与ではないため、贈与税ではなく所得税の対象
〇扶養義務者からの生活費や教育費▶配偶者・親・子・兄弟姉妹などから、通常必要と認められる範囲内で受け取った生活費や教育費
〇社会通念上相当と認められるもの▶香典・花輪代・祝い金・年末年始の贈答・見舞金など
◆基礎控除
贈与税の基礎控除=110万円(年間)
贈与税の計算と納付
①暦年課税
課税価格の計算
1年間(1/1~12/31)で贈与された財産を計算します。
本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産=課税価格
基礎控除
課税価格から基礎控除を差し引きます。
課税価格-基礎控除(110万円)
贈与税の税率
基礎控除後の課税価格×税率-控除額
贈与税速算表を用いて計算しますが、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した受贈者(贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上)は、特例税率を適用することができます。
贈与税の税率
|
贈与税速算表(一般贈与財産用<一般税率>) |
||
|
基礎控除後の 課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
― |
|
300万円以下 |
15% |
10万円 |
|
400万円以下 |
20% |
25万円 |
|
600万円以下 |
30% |
65万円 |
|
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
|
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
|
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
|
3,000万円 超 |
55% |
400万円 |
|
贈与税速算表(特例贈与財産用<特例税率>) |
||
|
基礎控除後の 課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
― |
|
400万円以下 |
15% |
10万円 |
|
600万円以下 |
20% |
30万円 |
|
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
|
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
|
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
|
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
|
4,500万円 超 |
55% |
640万円 |
②相続時精算課税
「1年間の贈与額-基礎控除(110万円)」の累計額-特別控除(2500万円)×20%
※2024年1月1日以降の贈与について110万円の基礎控除が設けられました。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、国内の「居住用不動産」または「居住用不動産の購入資金」の贈与をする場合で一定の要件を満たせば最大で2,000万円が課税価格から控除できる制度です。
この控除は、基礎控除110万円とは別に適用できるので、合計で2,110万円までの贈与を非課税にすることができます。
この制度が適用される要件として・・・
〇婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与であること
〇過去に同一夫婦間でこの特例による贈与を受けていない
〇贈与される財産が居住用不動産またはその取得のための金銭
〇贈与を受けた翌年の3月31日までに、その不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
また、この適用を受けるには、納税額がゼロであっても「贈与税の申告」が必要となります。
贈与税の非課税措置
◆住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
直系尊属(父母・祖父母など)から住宅購入資金の贈与を受けた場合に一定の金額までが非課税になります。この制度は暦年贈与の基礎控除や相続時精算課税制度と同時に適用を受けることが可能です。
〇贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を購入
〇贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上
〇所得金額が1,000万円超2,000万円以下▶住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下まで取得可能
〇所得金額が1,000万円以下▶住宅の床面積は40㎡以上240㎡以下まで取得可能
〇非課税限度額は、「一般住宅」が500万円「省エネ等の住宅」は1,000万円
〇適用期間は、2026年12月31日までの住宅の取得が対象
◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属(父母・祖父母など)が子や孫などに教育資金を贈与した場合に一定の額が非課税になる制度です。この制度の適用を受けるには金融機関で専用の口座を開設し、金融機関経由で所轄税務署長に申告する必要があります。
〇贈与者は、父母や祖父母などの直系尊属
〇受贈者は、30歳未満の子や孫で前年の合計所得金額が1,000万円以下
〇非課税金額は、学校に支払う教育資金で1,500万円、学校以外の教育資金は500万円までが上限
〇適用期間は、2026年3月31日までの贈与が対象
◆結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
直系尊属(父母・祖父母など)が子や孫などに 結婚資金や子育て資金を一括で贈与した場合に一定の額が非課税になる制度です。この制度は暦年贈与の基礎控除や住宅取得資金贈与の非課税措置、教育資金の贈与の非課税措置などと同時に適用を受けることが可能です。
贈与税の申告と納付
⑴贈与税の申告
贈与税の申告書は翌年の2月1日~3月15日までが提出期限となっております。
2贈与税の納付
贈与税の納付は申告書の提出期限である3月15日までに金銭での一括納付となっております。
また申告書の提出・贈与税の納付共に受贈者の居住地を管轄する税務署です。